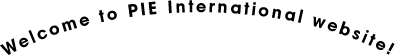さとゆめ 嶋田俊平さんインタビュー 前編

課題をビジネスチャンスに裏返す
―まずは沿線まるごとホテルプロジェクトについて教えてください。
2020年頃に構想がスタートしました。JR東日本のスタートアッププログラムというアクセラレーションプログラムに参加して、そこではじめて「沿線まるごとホテル」というコンセプトを提案したんですね。ベンチャー企業がJRと協業するためにプレゼンして、良いアイデアにJRさんが実証実験費用を出してくれて、テストをするっていう。それでうまくいけば、JRさんから出資が受けられたり、JRさんと共同出資会社を作るような。それに応募して採択されたのが2020年です。
―沿線まるごとホテルのアイデアについては、村まるごとホテルがきっかけだったのでしょうか。
小菅村でやっている「NIPPONIA 小菅 源流の村」というホテルがあって、それから始まったプロジェクトです。小菅のホテルは、観光客が2倍に増える中で、おじいちゃんおばあちゃんがやっているような旅館・民宿がどんどん減っちゃって、観光客は増えているけれども泊まるところが足りないと。その中で新しい宿泊事業を作らないと、その地域にあまりお金が落ちない。お金が落ちなければ雇用も生まれないし、700人の人口を維持するのも難しいということで、新しい宿泊施設を作ろうという話になりました。ただ、大きなビルやホテルだと大変だし風景が変わっちゃうし、そういった時に「空き家が100軒あるぞ」っていう話が入ってきた。ここがひとつポイントなんですけど、空き家って課題ですよね? 地域課題。空き家があると治安が悪くなるとか、ボロボロになって景観が悪くなるとか、維持費がかかるとか、いろんな問題があるんですけど、その地域課題を資源としてビジネスのチャンスに裏返すというのが重要なことなんですよね。地方創生は課題しかないのでその課題をうまく使う。その100軒の空き家が全部客室になったら村の中に散らばる形で100室のホテルができると。そしたら、700人の村がひとつのホテルに見えてくるんじゃないかっていうアイデアで今やっています。

―なるほど、それを沿線全体に広げていったのでしょうか。
小菅村の話を続けると、もうひとつは空き家が客室になるだけではなくて、村の道路をホテルの廊下に見立てたらどうかとか、道の駅はホテルのロビーだとか、村の温泉施設はホテルのスパとか、村の商店はホテルのギフトショップとか、村人はホテルのキャストとかっていう世界観を作っていって、いろんなところで「村の道路はホテルの廊下だからきれいにしよう」ということで花を植えたりとか、空き缶が落ちてたら拾うとか、ホテルに泊まっていた方が迷子になったら村の方が案内してくれるとか、家にあげてお茶を出してくれるとか、そんな形で心温まるエピソードが村中で広がっていくと、村がどんどんきれいになっていって村のおもてなしがどんどん溜まっていく。すると、村にもちゃんとお金が落ちるし、めぐりめぐって我々のホテルの集客や経営もうまくいくんじゃないかっていうのが小菅村でやっていることです。青梅線の青梅・奥多摩間は、森の中を電車が走り、自然豊かなんですけど過疎は進んでいるんですね。若い人がどんどん出ていっちゃって、人口が減って、空き家が増えて。青梅駅と奥多摩駅間は13駅あるんですけど青梅駅と奥多摩駅以外は全部無人駅なんですよ。小菅村と同じような状況になっているんですけど、これも「無人駅」とか「空き家」とか、そういうものを何かしらビジネスチャンスに変えていくというか、「コンセプトでひっくり返す」のがポイントなんです。

―ひっくり返すことこそが、デザイン的な視点だなと思います。どのようにひっくり返しているのでしょうか。
課題を資源にひっくり返すというところなんですけど、もっとわかりやすく言うと「空き家」や「無人駅」「人口減少」という課題って、暗くなるというか、もやもやするじゃないですか。それをワクワクにひっくり返す。たとえば、「無人駅がホテルのフロントになったら面白い」とか、「沿線の空き家が客室になったら面白い」とか、「沿線の集落の住民の方がホテルのキャストとなってお客様をお出迎えしたら面白い」とか。基本はそういうことなんですけど、村まるごとホテルと沿線まるごとホテルが違うのは、村っていうのは行政界が決まっているんですよね。ちゃんと線が引かれているんですよ、地図上に。でも沿線って、どこからどこが沿線かってわからないじゃないですか。沿線ってすごくふわっとした概念なので。沿線という言葉も必ずしもみんなが良い印象を持っているわけではない。無機質な、「沿線開発」とか。ではどういうふうにしたらお客さんが「あ、いいな」って思うかとか、地域の方々が「応援しよう」って思うのかというところは結構悩んだポイントなんですけど、その時にひとつこうしたらいいんじゃないかって仮説を立てたのは、奥多摩の人と話してると、集落というものにすごく愛着とかアイデンティティを感じているんですね。「俺は白丸集落だ」とか「沢井集落だ」みたいな。なので、いきなり沿線っていわずに、集落単位で集落の人たちを巻き込みながら、「ホテルの営業手伝って」とか、「お客さんガイドして」みたいな形でやっていくとうまくいくんじゃないかって。集落とセットで駅があるんですよ。だから、駅と集落セットで作っていこうと。簡単にいうと、鳩ノ巣駅と鳩ノ巣駅の近くに棚澤という集落があるので、鳩ノ巣と棚澤集落をセットにする。鳩ノ巣駅をホテルのフロントにして、棚澤集落の空き家を客室にして、棚澤集落の方々に手伝ってもらうみたいな。

この、鳩ノ巣・棚澤みたいな、駅と集落というセットをどんどん増やしていこうと思っているんですね。そうすると、ゆくゆくは青梅線っていうものがホテルのエレベーターみたいな役割を果たしてくれるんじゃないかと。ホテルって縦に長いじゃないですか。エレベーターで上がって、いろんなフロアに降りるじゃないですか。大浴場のあるフロアとか、レストランのあるフロア、あとは自分が泊まっているフロアとか。バーとかロビーとか。フロアに降りるみたいに、無人駅に降りる。そんな感じで、集落というフロアを楽しむというようになってくれればいいんじゃないかって。縦に長いホテルを横に寝かすような。そうすると、青梅線っていうものが、無理矢理ですけど「まるごとホテル」に見えるんじゃないかっていうのが我々のコンセプトです。森があって川があって、自然がたくさんあるんですけど、点で見ても特別なものは何もない。それを、コンセプトでくくると面白く見えてくる。小菅村でもそんなことをやってきてるんですけど、それが僕らのやり方ですね。世界遺産とか重要文化財とかがなくても、コンセプトで沿線をまるごと楽しもうっていう観光が成功すると、それが他のどこでもできるようになる。これが、僕らが目指していることです。
―「ワクワクに変える」という発想には嶋田さんのロマンチックさが垣間見える気がします。どのようにたどり着いたのでしょうか。
さとゆめを立ち上げて今11年、その前は9年間コンサル会社で働いていて、20年こういう仕事をやっているんですけど、地域資源を使って事業を作るみたいな、そういう経験の中で現在の発想の仕方に行き着きました。地方創生や地域づくり、街づくりっていうと「課題を解決しよう」っていうのがすごく強いんですよね。街づくりのワークショップとかに行くと、まずなにをやるかっていうと、街の課題をみんなでできるだけたくさん出していくんですよ。少子化とかバスの本数が少ないとか、店がないとか、若い人が出ちゃうとか、数えきれないくらいいっぱいあるんですけど、課題をいっぱい出した次に、その課題をグルーピングするんですよ。交通の課題、住まいの課題、教育の課題、観光の課題、そのグループごとに課題解決の方向性を探していきましょうと。たとえば、インバウンドを誘致するとか、補助金とか、課題をあげてグルーピングして、それらの解決策を考えていくと。そういうことをしていくと、どんどん気分が暗くなるんですよ。最後には「いやあ、もうなにやってもダメだわ」って。とても立派な、すごく網羅的に課題が出された体系的な計画ができるんですけど、でもその計画ができたあとはなにも動かないっていうことが起こるんですね。っていうのが、今日本中で起こってるんですよ。僕はその中にいるのですごくわかりますし、申し訳ないなって思うんですけど、そういうことが起こってて。ある時に「課題なんて出しててもしょうがないな」って思ったんですよね。なので課題を出すということをやめたんですよ。課題なんてどこだって同じだし、空き家とか少子化とか高齢化とか、変わらないので。だから課題を出すんじゃなくて、みんなで夢を出しましょうと。
夢や願いは収斂する
―素敵ですね。
奥多摩がどうなったらいいですかね、とか。昔から「こうなったらいいな」と思ってたけどまだやれてないことってありますか、とか。昔の、まだ人口が多くてにぎやかだった時に楽しかったことってなんですか、とか。そしたら、映画館があってとか、パチンコ屋があったとか、村のお祭りがすごいにぎやかで出店がたくさん出て、そのあとみんなで飲み明かしたとか。そういうのが出てくるんですね。そういうふうに夢を出すと、みんなが「いいねいいね」となるんですよ。「いいね、それやろう」「俺もそうなったらいいと思う」とか、「あれ楽しかったよな」みたいな。課題ってどんどん発散していくんですね、いっぱいあるから。でも、夢とか願いとかって収斂(しゅうれん)していくんですよ。みんなが乗っかってくるというか。そうなると、最後みんなが実現したいものが一個ぽろって落ちてくる。「それじゃあみんなでやろうか」となるんですよ。なので、自分は街づくりの手法として「課題を出す」というのはもうやめていて、みんなで「こうなったら面白いよね」というものを出すようにしています。
―真逆のアプローチですね。
その中で、JRさんとも「今青梅線で無人駅がすごく増えていて」とか、「お客さんが減っていて」とか、「電車運賃もどんどん減っていて」みたいな話があったんですよ。「沿線まるごとホテル」っていうコンセプトは、最初からいきなりポンとは出てこなかったんですよ。最初は「東京無人プロジェクト」みたいなディスカッションをしたんです。無人駅だからこそできるワクワクなことをみんなで考えようと。たとえば、無人駅がバーになる「無人バー」とか、無人駅が映画館になる「無人シアター」とか、あとは自転車のレンタサイクルの拠点として「無人サイクルステーション」を作るみたいな、人がいなくて駅前が閑散としているからこそできることってたくさんあるよね、と。無人ギャラリーとか、無人プラネタリウムとか。そんな感じでみんなでアイデアを出していって、そうした時に「東京無人ホテル」みたいな、無人駅がホテルのフロントになって、さすがに駅舎には泊まれないけど、集落の近くの空き家を客室にして、改札口を出たらそこはみんなホテルになっていると。無人駅から始まる新しい宿泊体験みたいな、そういうのって面白いですよね、という話から、それが駅ごとに増えていったら面白いよねというさっきの話につながって、沿線まるごとホテルというようになっていって、ではJRさんのスタートアッププログラムに応募してみようと。

「沿線まるごとホテル」実証実験時のレセプション
―このプロジェクトはコロナ禍を挟んでいたと思うのですが、大変だったことやコロナ禍によってプランが変わったことなどはありますか?
多少開業が遅れたというのはありますね。ただまあ、それはネガティブというよりかは、じっくり設計士さんを探したり、じっくり設計したり。あと僕らはホテルをやりたくてやっているわけではなくて青梅線を活性化させるのが目的なので、ホテル事業以外もトゥクトゥクのレンタルとか、期間限定の宿泊プランをやってみたりとか、「酒列車」っていって青梅線の中でお酒が飲めるものとか、いろんなことをやってきたんですね。客室自体はまだ開業していないんですけど、沿線まるごとホテルというコンセプトで3年くらい活動していて、もうメディアにめちゃくちゃ出まくってるんですよね。まだ客室できてないのに(笑)。なんにもできてないんですけど、コンセプトと活動だけでずーっとやってるんですよ。そうすると、みんなに沿線まるごとホテルが「ある」というか、始まってる、開業してると思われるんですよ。で、いざ来てみるとまだ客室ない、みたいな(笑)。それもそんなにネガティブなことではなくて。それで昨年「ジャパン・ツーリズム・アワード」という、国が主催するその年一番優れた観光の取り組みを紹介するアワードがあるんですけど、そこで最高賞の国土交通大臣賞を獲得したんですね。まだ開業していないホテルがですよ?モノ消費からコト消費って言うじゃないですか。今の世の中の人たちはマイカーとかマイホームとか、ブランドとか、「モノ」をあまり求めてなくて、「ここでしかできない体験」とか「地域とか社会に貢献する」とか、「誰かと大切な時間を過ごす」とか、そういう「コト」に関心が移ってきてる。ワクワクするようなプロジェクトに参加するとか。それをすごく感じました。だからまだ客室がないのに賞を獲っているし、もう大きなムーブメントになっているし、若い人たちもいっぱい集まっている。

沿線単位のDMO
―色々なプロジェクトは今後も続けていくのでしょうか。
そうですね。ホテル事業だけでなく、やれることは全部やっていきます。最初は沿線まるごとホテルっていうコンセプトで始めたんですけど、この客室ができない3年間にいろいろトライしたり、みんなで話している中で、「沿線まるごと○○」というのがどんどん出てきて。「沿線まるごとラボ」、沿線の課題解決というか、沿線で新しい光景を生み出すラボとか、あとは「沿線まるごとモビリティ」、トゥクトゥクとか自転車の貸出ができたり。あと「沿線まるごとDMO」っていうのも作ろうとしていて、「DMO」っていうのは新しい観光協会みたいなもので、その地域に人の流れを生み出す戦略を策定して実行する、Destination Management Organization(デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーション)っていうんですけど、観光庁とかがこのDMOを今すごく後押ししているんです。都道府県単位のDMOだったり、市町村単位でもあったり、たとえば「九州まるごとDMO」とか。その中で我々は沿線を圏域としたDMOっていうものを作ろうとしているんですね。この青梅線に新しい人の流れを生み出す戦略を作って実行するっていう。そういうことをやっていたり、あとは「沿線まるごと保育園」っていうのをやってみたいなと。「保育園留学」って知ってますか?

―聞いたことがないです。
田舎に親子で3日とか、長ければ2週間くらい行って、現地の保育園に子どもを預けて、その間親は自然の中でリラックスしてリモートワークをするっていうのが今広がってるんですけど、そういう保育園留学をこの沿線でやるとか。
―確かに保育園もセットは今までなかったですよね。セットであれば家族で来やすくなりますね。
そんな感じで「沿線まるごと○○」みたいなものをどんどん作っていこうかなと考えていて、たとえば「沿線まるごとカレー」とか。沿線の食材を使ったレトルトカレーを商品化する、みたいな感じのことを今やろうとしているんですよ。
―ホテルからそこまで広がるのがすごいですね。元々の沿線まるごとプロジェクトや実験的なホテルはどういう方が利用されているのでしょうか。
小菅村のホテルも同じようにストーリーやコンセプトで勝負しているのですが、小菅村の方は2019年に開業して4年半くらい経っていて、同じような客層になるんじゃないかなと思っているのですが、30代〜40代で50%くらいです。古民家ホテルなので年配の方が結局多くなるんじゃないかと思っていたら、30代〜40代の方々がメインで、20代が20%くらいいるんですね。だから20代〜40代で70%くらい。結構若いですよね。私の感覚からすると、さっきのモノ消費からコト消費の話になるんですけど、若い人がこういうコンセプチュアルなことにすごく興味があるんだなって思います。ちゃんとコンセプトやストーリーを丁寧に発信していくと、若い人たちにマッチして興味を持ってくれるんだなって。
―発信の仕方で具体的に工夫した点はありますか。
やっぱりSNS、インスタグラムがメインですかね。あとはウェブサイトとか。自分でいうのもなんですが、すごく良い感じになってます。動画で自分たちが表現したい世界観を表したり。写真とか動画、文章ひとつとっても丁寧に物語を紡いでいます。

(後編に続く)
取材協力:株式会社さとゆめ